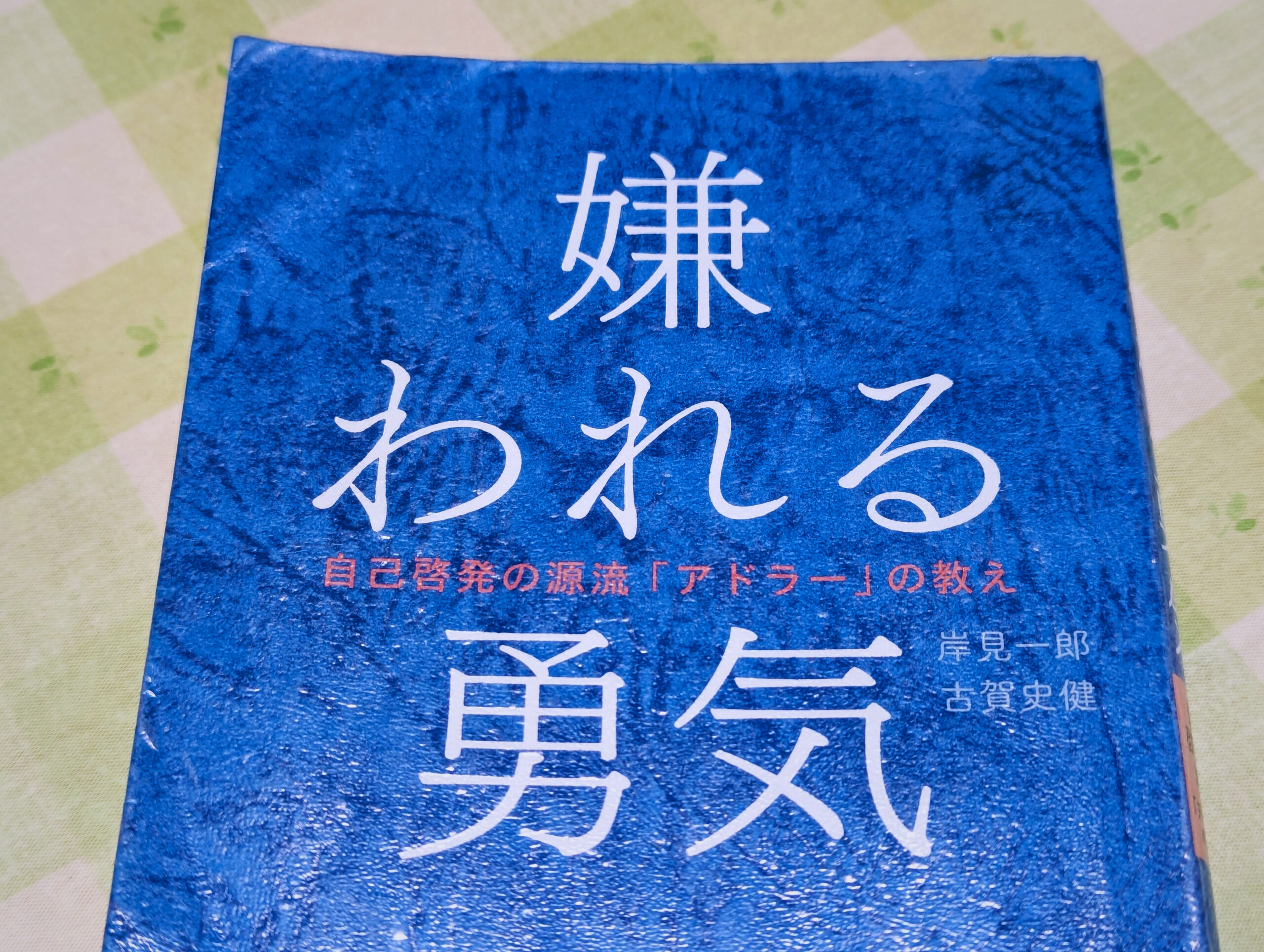前から読んでみたいと思っていた本と図書館で出会いました。
『嫌われる勇気〜自己啓発の源流「アドラー」の教え〜』
「心理学の三大巨頭」の1人と称されるオーストリアの精神科医アドラーによる心理学を解説している本です。
アドラー心理学とは、ざっくり言うと
人が幸福になるための考え方と方法。
この本は、哲人と呼ばれる哲学者と青年による2人の対話によって物語がすすみます。
「人の悩み事の原因は全て対人関係にある」
冒頭で、哲人がそう言い切ってしまうのですが
そんな哲人に、
「原因がすべて対人関係にあると、どうして言い切れるのか?!」
青年が哲人に次から次へと疑問を投げかけます。
青年の疑問に「そうだ!そうだ!」と共感。
読み進めながら、自分の中にある相手への期待、自分の弱点、人との接し方について、多くの気づきを得ました。
普段はスキマ時間に読書してますが、今回は
「スキマだけじゃ時間が足りん!!」
と思えるほど夢中で読みました。
この本を読み終えた頃には
「世界って思ったより優しいのかもしれない…」
と哲人の言葉に触れ、温かいものに包まれたような気持ちに(*´ω`*)
これからどう生きていけばいいのか、人生の指針のようなものが見えた気がします。
対人関係の中でも、いちばん良好でありたい子どもとの関係。
今回は子育てにフォーカスして自分の考えをまとめました。
目的論(物事にはすべて目的がある)

「トラウマのせいで恋愛ができない」
トラウマという過去の出来事が原因で恋愛ができないとい「原因論」に対して目的論とは
「恋愛をしたくない」という目的があるから「恋愛をしない」という行動を選んでいるという考え方です。
この考え方…目からウロコでした。
たとえば、子育てが忙しくて自分の時間がないっていうのは
自分の時間を確保しないという行動を選んでいた。
「子どもを優先しなくてはならない」「周りの人も子どもを優先しているから」と思っていたのかもしれない。
たとえば、学生の頃に対人関係でつまづいたので、今も人付き合いに対して苦手意識がある、というのは
もし嫌われたら傷つきたくないから、「人付き合いは苦手」と言って深く関わらないような行動を選んできたのかもしれない。
原因論による、自分の行動の多さに気づきました。
過去や環境のせいにしてたけど、そうなるように行動してきたのは自分。
つまり、
行動は選ぶことができる!
子育てが忙しくても自分の時間を確保する!と思えば確保できるし、人付き合いが得意という行動も選べる!
私を縛りつけていたものが、ゆるゆると解けて、体がフワッと軽くなりました。
全体論(1つ1つバラバラに見るのではなく全部ひっくるめてみる)

「最近、息子がやる気なさそうに見える」
全体論は「やる気がない」という表面的な行動をみて「怠けている」と判断しないで、
身体の状態、感情、考え、環境、目的などのあらゆる要素を全部ひっくるめて理解しようという考え方です。
一番身近な存在である家族と過ごす中で、表面的な行動から推測することって多いのですが
たとえば子どもが
「片付けをしない」「話を聞いていない」
といった、親からみると問題とよばれる行動が起きたときにこそ、その背景にあるものが何かを考える。
私達はネガティブなものに反応してしまう生き物なので
周りからの刺激に対して、自分がネガティブな反応をしそうな時は、すぐに反応しないで考えを巡らせて行動したいところです。
悪い面だけじゃなく、良い面も探してみる!
自己決定性(自分の行動や人生を自分で決めること)

アドラー心理学では、自分の課題に集中し、自分の行動を自分で決定することの重要性を強調しています。
たとえば、服を買うときに店員から「お似合いですよ」と勧められても、自分が欲しいと思えなければ買わないし、欲しい服を自分で選んで買います。
自分の行動は自分で決定することに対して、相手の行動は相手が決定することを忘れちゃいけないと感じました。
特に子どもに対して。親の都合に合わせて欲しい場面がたくさんあります。
暑い日、娘が長袖を選んだとき「半袖着たほうがいいよ」と私が伝えると、納得しない様子でいつまでも着替えないことがありました。
その様子に見かねて
「暑いから言ってるんでしょ」
と着替えたくないなら着替えなくていい、と突き放した言い方をすると
娘は不満を抱えた様子で着替えましたが
娘が長袖を選んだのなら「半袖の着替えを持っていく」という選択があることを伝えればよかったな、と。
そもそも、暑い日に長袖を着るとどうなるかを身をもって体験することで、次からは半袖を選ぶかもしれない。
私が娘の自由を奪ってる!!(´゚д゚`)
そう気づいてからは、娘の服選びに口出ししなくなりました。(笑)
助けを求められたら助言する程度で。
自分で決めるから、納得できる!
認知論(人がどのように物事を理解し、考えるか)

雨が降ったとき。
親は「洗濯物が乾きづらい」と感じ、子どもは「水たまりで遊べる」と感じるように
認知論は1つの事実に対して、人それぞれ解釈が違うので捉え方も変わるという考え方。
たとえ相手が共感してくれたとしても、自分の考え方と相手の考え方は違う。
自分と相手の考えが一致したとしても、それはほんの一部分。
みんながみんな同じ考えではないのは、わかっているようでわかっていないもの。
日常の会話で、自分の都合のいいように解釈しがちだなぁと感じることがあります。
「アレなんだけど」
「あーアレね!」
アレが合致してなかったり。(笑)
会話の中では主語が抜けがちなので
相手が気持ちよく話してるときに水をささないよう
自分の解釈が合ってるのか確認しながら会話をする。
ラクなことではないけど
誤解からトラブルに発展するよりはマシ!
自分から相手に話すとき、「伝わりやすい伝え方」を意識したいです。
対人関係論(人は人との関係性で生きている)

相手が存在があるから、自分も行動したり感情が動く。
自分の感情や行動と相手のそれが互いに影響して、対人関係が作られるという考え方が対人関係論。
人が幸せを感じるためにアドラーが重要視しているのが
できない自分を「ありのまま受け入れる」という自己受容、
「自分はここに所属している」という所属している感覚、
「仲間を信頼できる」という他者信頼している感覚、
「仲間に貢献している」という他者貢献している感覚。
つまり「自分への執着」を「他人への関心」に切り替えて
自分は社会や共同体の一員だと感じて
人とつながり、貢献する感覚が持てると幸せでいられるという。
職場では仕事を通して「所属感」「他者信頼」「他者貢献」を感じやすい一方で
家ではどうだろう?と考えたときに
「片付けてほしい」「手伝ってほしい」「早く支度してほしい」と
要求が多くて、他者貢献してる感が薄れてることに気づきました(笑)
哲人によると、
家事をやらない家族に対して「なんで私ばかり家事やらなきゃならないの」と捉えず
「家族の役に立ってる」
と考えるのだそう。
家族が私に何かしてくれると勝手に期待してるから、自分の期待どおりにならないと感じたときに不満や要求が生まれてきたのか…と反省。
私が家族の役に立つために何ができるか。
やってもらうことばかり考えないで
まずは自分にできることをやる!
大切な居場所を守りたいと感じました。
課題の分離(自分の課題と他人の課題を分ける)

人との距離感って、こんな感じでいいのね!
「嫌われる勇気」を読んで、心が軽くなれた考え方です。
子どもが宿題をするかしないかは、子どもの課題。
子どもが宿題をしないことでイライラした感情になるのは親の課題。
親は自分がなぜイライラするのか、自分の課題と向き合う必要がある、というのが課題の分離の考え方。
たしかに宿題をしないで困るのは親じゃないですね。
課題を分けると「あれ?どうしてイライラしてたんだっけ?」ってなります。(笑)
『嫌われる勇気』の2人の会話の中で
「誰かを信頼したところで裏切られる」
裏切られることへの恐怖を含んだ青年のセリフに
「裏切る裏切らないを決めるのは他者の課題」
哲人がバッサリ斬っていたのが印象的でした(*´∀`)
裏切るという行動は、自分ではなく相手の行動。
ヒトの心の中を読むことができないので、相手の行動はどうすることもできません。
自分にできることだけをする、に尽きるわけですね。
人間関係が上手くいかない時ほど相手との距離が近すぎるかもしれないので、
干渉し過ぎず、され過ぎず
ほどよい距離感を保つために「課題の分離」を使いこなせるようになりたいです。
読んだあとに感じたこと

『嫌われる勇気』の哲人の言葉ひとつひとつのメッセージ性が強いので、対人関係で悩んだときはこの本を読んで哲人に励ましてもらいながら、原点に立ち返ろうと思います。
「自分にできること」「他人の課題を見極める」
これができれば、かなり気持ちがラクになると思うので意識していきたいです。
子どもたちの行動はいつも想定外で「なんでそうなるの?」の連続で、この記事を書いてる時も子どもたちは家の中を騒ぎ動き回っていますが、
「全体論、全体論、全体論」
と唱えると、あら不思議。
「あの子達の行動には理由があるんだ」と落ち着けたので、「全体論」と書いた紙を部屋の見える場所に貼っておこうかな、と思いました( ^∀^)